東松戸地域の魅力-紙敷石みやの森-
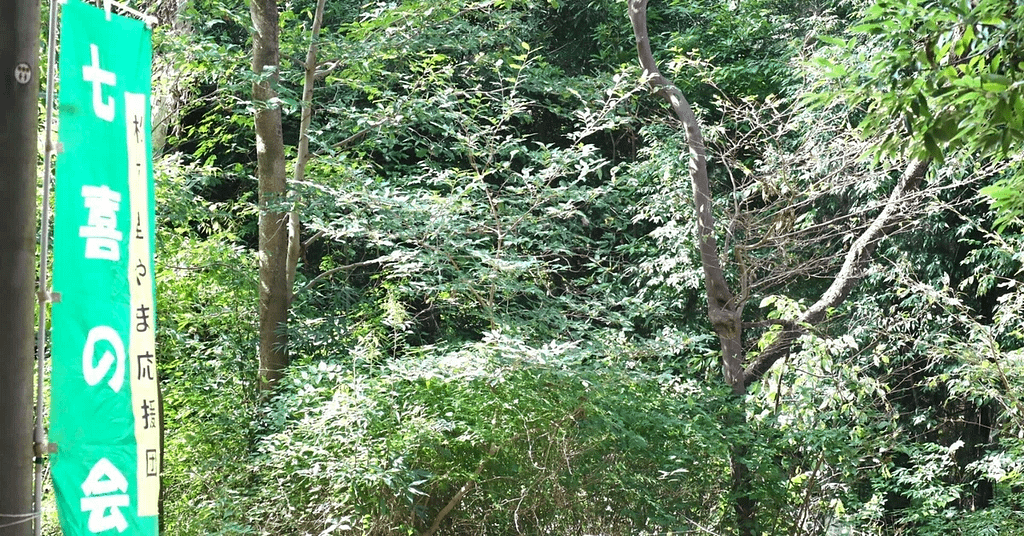
はじめに -地域のつながり-
この日(9月27日)は、JR武蔵野線東松戸駅で下車し、西口広場から「紙敷石みやの森」へ向かうため道路を右折して歩き始めました。
5分位すると、小高い丘には多数の幟が目に入り、近づいてよく見ると東松戸中央公園で行われている「東松戸まつり」でした

東部地区の各種団体による実行委員会が主催し、地元の小中学校の皆さんをはじめとする多くのボランティアが活躍していました。
ステージは音楽発表・踊りなどバラエティーに富んだ出演、周辺は多数の出店と人出、とたいへんな盛況ぶりでした。
東松戸地域の発展する状況を反映する多数の様々な人たちの融和する光景が見られました。



東松戸中央公園から近くの「東松戸ゆいの花公園」前を通って松戸市立松戸高等学校野球場脇に「紙敷石みやの森」があります。
ゆいの花公園は、ご近所に、街に“ゆいの花”を咲かせましょう、という名前の由来があるように、『市民一人ひとりが「花」によって結ばれ、「花」を通じて輪が広がり、心の潤いや安らぎを感じてもらえれば』という思いを“結(ゆ)いの花”という名に込めています。
東松戸ゆいの花公園ってどんなところ?www.city.matsudo.chiba.jp
松戸市のような近郊都市は、多くの人びとが各地より集まり、近隣の暮らしをともにするという特徴があります。「ゆい」の場は、「まつり」も「里やま保全活動」も人びとのつながりによって行われています。

紙敷石みやの森へ
東松戸地域は、東京の近郊都市として発展してきた松戸市において近年注目されているところです。
全国各地より移り住んできた人びとが“結い(ゆい)”の活動として花の栽培などに携わると同様に、近くのあるがままの自然を感じる森で共に実際の具体的な作業をすることにより様々な里やま保全活動をする場が「紙敷石みやの森」です。
「七喜の会 紙敷石みやの森」は、近くの畑地に農園もあります。

市立松戸高等学校野球場脇と農園の小道を抜けると、「七喜の会」の幟が目にとまり、事前に活動日参観の了承を得ていましたので、森の中へ。

その日は、暑苦しい天候でしたが、森に足を踏み入れると、冷やっとしたさわやかさを肌で感じることができました。
幟の近くで作業をされていた女性の皆さんにあいさつをしますと、
「代表の活動場所に案内します。」
森の冷涼な空気を吸いながら歩いていきますと、きれいに整備された通路が続いていました。
「よく整備されていますね。たいへんな作業だと思うのですが・・・・・。」
「春から夏の間は雑草がいっぱい伸びます。下草刈りもよく行う作業です。」

自然に向き合う人のつながり
案内されましたところは、農園とグランド近くの広場で代表池村信さんと事務長山下烈さんがテーブルづくりの作業をされていました。

早速にあいさつをしてから活動の内容を伺いますと、
「『行政・地権者と私たちボランティアと市民の三位一体』となった活動がここで行われています。」
と説明があり、松戸里やまボランティア入門講座の7期修了生とその後入会された皆さんで活動を継続していることを話されました。
中でも、市民、特に子供向けに、「オープンフォレストinまつど」や「森あそび」などが開催され、広く開放されていることを強調されていました。
その「森あそび」は、「NPO 法人こどもっとまつど」と「松戸里やま応援団」が協同企画し、小学生親子の皆さんが参加して、昨年までに4回開催されてきました。
となりの「野うさぎの森」にも活動の場を広げ、自由に散策や、クラフトづくりやハンモックなどで森の楽しさを満喫していました、と伝えてくれています。
特に他の森では、「囲いやまの森」の活動が様々なユニークな内容で取り組んでいるので参観することを推奨したいと強調されていました。
紙敷石みやの森・七喜の会は2009年(平成21年)に活動を開始しました。その後には新規の会員も加わり、「紙敷石みやの森通信」の発行実績が500号以上となり、その充実ぶりを物語ります。
森の地図と活動森の紹介(地図と活動) 松戸の森一覧 森の地図と活動日 里やま活動・ナラ枯れ対策・チッパーで森を綺麗に!・森のごみ処理・森matsudo-satoyama.org
その通信によりますと、
「『石みやの森』の命名の由来としては、この森には地権者様の祖先が代々お祀りしてきた石詞があります。僅かに読みとれる刻字には建立延宝四年(1676)辰12月吉日とあります。徳川四代将軍家綱の時世です。今でもご当主様は年2回神飾りを新しくして先祖から受け継いだ森を大切にお守りしています。会では石みや様を森の象徴として、守り育て次世代へ橋渡しするため『紙敷石みやの森』と命名しました。」
「特徴としては、江戸時代放牧場の馬が侵入しない様に築かれた野馬除け土手が残り、その江戸時代から続く里山でスギ、サワラ、ヒノキ などの針葉樹人工林と二次林と思われるクヌギ、コナラ、イヌシデ、ヤマザクラなどの落葉広樹林、スダジイ、シラカシ、ヤブツバキ、ヒサカキなどの常緑広葉樹、約70種の樹木が生育していることを紹介しています。」
近年は、虫食い被害への対応が避けられない状況となっており、従来から続けてきた里やまの保全活動に加え、農園での収穫体験なども組み合わせて取り組みを進めています、と述べられています。

手入れの行き届いた森を巡らせてもらい、出入り口付近に行きますと三人の女性が下草刈りの作業をされていました。

その中の一人に、
「いつごろから活動に参加されているのですか?」
と尋ねますと、顔をこちらに向けながら手を休め、
「一昨年、松戸市のサポートセンターの行事に参加しました際、こちらの会員の方と言葉を交わすうちに、森の活動を知り、とても新鮮で健康的な作業内容に興味が惹かれましたので、活動日に参加してみました。」
と話し終えると、すぐに手を動かし始めていました。
他の方は、どうなのかと思い、
「お仲間の方はどのようなことでしょうか? 他の方のことはわかりますか?」
と聞きますと、同様の仕草で
「あの方は私の知り合いで、森の活動に参加し、自然の中で清々しい気持ちになっていると体験談を話すと、興味をもってくれ、昨年から加わりました。」
と紹介をしていただくと、その方は和やかな表情をこちらに向けられました。
他にも様々な方々が、それぞれの境遇や理由などをもって参加しているとのことでした。
まとめ
「七喜の会 紙敷石みやの森」は古くからの里やま景観や歴史的な歩みを大事に保全する活動が重視されています。
里やまの歴史や活動を学ぶ子どもたちへのイベント案内や、昔ながらの農作業体験など親子活動を通して、歴史や文化を体感できる取り組みが行われています。
何よりも強く感じましたのは、自然のあるがままの営みに対して人のつながりを大切にされていることです。
そして、自然と人の関わることのできる地域の魅力を伸ばしていることです。
それらのことについて共に行う作業のねらいに一人でも多くの参加を呼びかける熱意をもった活動に取り組まれています。
<石橋>


