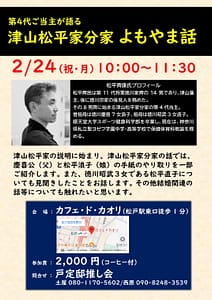江戸川・ふれあい松戸川の自然と川を考えるシンポジウムに参加して
主催 千葉大学国際高等研究基幹 共催 松戸市
2025.2.2 キテミテマツド9F

参加者:石橋一夫の報告・感想
各専門家の基調講演は、示唆に富む内容で、どれも今後の自然と川を考えるのに活かせるものであった。「関東エコロジカル・ネットワーク」の活動や「かわまちづくり」などが紹介され、その取り組みについては、地域における市民の活動と一体となって推進することが重要との視点を強調されていた。
中でも小中学生との活動は環境教育との関連で、自然の再生を計るように時間をかけて実践し、自然のバランスを経ていくとのことであった。特に外来水生植物のナガエツルノゲイトウ等は特定外来生物に指定され、著しい侵入・繁茂の生態が確認されているとの報告があり、多くの参加者が驚きをもって注目していた。
このような状況で市民の活動は、知る・学ぶ・調査の過程で事務局を中心に、つながることが重要な役割を果たすと主張されていた。
松戸市の「坂川の清流ルネサンス」取り組み事業などにも触れられ、成果も指摘されていた。だが、関連するテーマや内容としての事柄は少なかったように思えた。
私の関心事「江戸川河川敷等空間域活用事例」について空飛ぶクルマやドローンなどの質問したところ、他地域の取り組みにおいて、社会実験の段階ではじまっているが、まだ実際の報告例はないとのことであった。河川流域の自然とドローン活用事例等との関係については重要な視点であると認識していると、独立研究所中村氏、国土交通省松本氏とも述べられていた。
松戸市の河川清流課渡辺氏は、市においても河川敷域でドローンを飛ばすことができる取り組みも許可されているとして関心事にされていることを知ることができ、よかったと思っている。なお、渡辺氏は、取り組んでいる市の「ふれあい松戸川」事業については、通年のにぎわいを保つことがむずかしいとの課題を述べられていたのが印象に残った。
これらについて、地元の千葉大学大学院等関係者の力添えをいただきながら、市民活動を巻き込みながら関連分野の連携を図る企画・実践の場が設置され、取り組みの方向性が見出せるならば、市民シンポジウムの意義が評価されると思われる。