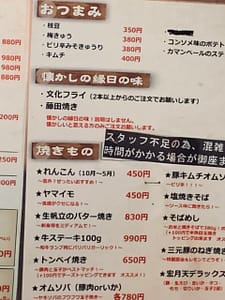「松戸ブランド」の普及促進を願って ―補説 ③―
「松戸」の心象風景と地域形成の関係性は?

私たちが「松戸」の風景や景観について心の中に描くイメージや感覚的な具体的な像は心象風景ともいわれる。
心象風景は、だれもがそれぞれに見たり聞いたりしたことを意識して描く印象的な像や景色とされるだけに個々によって異なる。「松戸」ゆかりの人の場合、歴史上のことも含めて、かつての出来事や体験を想起してある場所やその時の場面を心に描くことなどを指すことも可能と考えられる。私たちがそれらをイメージするときの季節、時間帯、場所などで構成される状況の変化がある。さらに、それらの場面などを認識するときの暮らしや個人的な経験にともなう心情のあり方などもある。
したがって、その人の心象風景そのものは、多種多様に変わることがある。つまり、これらを活用して自由に、改めてその人自身の異なる人生を想い描きながら、「松戸」の風景や景観のあり様を描くならば、これからの地域形成に及ぼす発展的な具体像を提起することもありうることになる。様々な事例を通して人の暮らし方の多様性を探り、地域発展に寄与することも可能性を秘めていると期待される。
一例をあげてみたい。江戸川沿いに納屋河岸といわれる伝統的な地名がある。江戸時代の早い時期から江戸川の水運を利用した河岸があったとされ、松戸河岸には明治時代にも納屋河岸の青木家と渡船場河岸の梨本家が通運会社を継続させてきた歴史が伝わる。今も青木船問屋の復元された塀がある。その場に立ってこの付近で鮮魚などの荷積みをする人びととロボットなどの動きを想像してみる。往時をしのぶ場合と、これから先の水陸両用車・空飛ぶクルマなどで江戸川空間を利用した場合などだ。鉄道やトラック輸送などの普及により衰えた江戸川水運も、交通機関などの変化によって新たな見方考え方に基づく「松戸」の再興される可能性も予見されるかもしれない。
それぞれの方々がもついろいろな心象風景の多くと地域の発展を考え合わせ、新たな地域形成の雰囲気づくりを醸成していきたい。多くの人びとの投稿を期待し、願う。