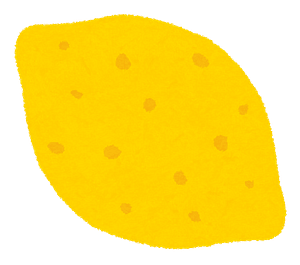「松戸ブランド」の普及促進を願って ―補説 ⑧―
「松戸」の河岸と結びついた食材やこれからの産業・交通・観光

納屋河岸は江戸時代に栄えた松戸河岸の一つで、今もその歴史を伝える、船問屋であった青木家には白壁に黒塗りの板塀がある。水運による銚子からの鮮魚を日本橋の魚河岸まで運ぶ際、松戸河岸は利根川沿いの布佐より手賀沼の南を通って松戸に至る「なま(鮮魚・生)街道」の中継地であった。また、近郷の穀物、野菜、魚、薪、炭などを江戸に輸送する物流拠点として大いに繁栄した。
海と川で囲まれた房総半島には、江戸時代の中期以降、日本の伝統的な調味料として醤油・味噌・みりんがあり、今も有名なところに銚子・野田の醤油、流山のみりんが挙げられる。
松戸にもかつて同様の醸造所があったという歴史があり、この利根川・江戸川流域に根付いた伝統的な調味料は、日本食文化のブームと相俟って今や世界に広がっている事実に注目をしていきたい。
江戸時代における大消費地江戸の発展と結びついた「松戸」の納屋河岸のもつ実績とこれからの産業・交通・観光などを想像してみたい。
先に触れたように、これからの展望として空飛ぶクルマや水陸両用車の自動運転などが現実化されてくる可能性はそれほど遠いことではないと思われる。そのような際に、近郊農業地や水産資源の輸送基地の役割を担う「松戸」の展望は大きく開かれているし、将来性も期待される。伝統的な調味料を活用した近郊野菜・水産物の加工・販売や店舗の展開などの協業体制を築き、江戸川流域の関連企業との連携を模索することも可能となる。
さらに、近隣畜産品などを含めての食材を活かした調理法を開発し、調理講習会などのイベント開催や開発商品の伝達・普及を計っていくことも有用なことと考えられる。調理講習会などの体験型のイベントには、他に「戸定歴史館」の見学や「21 世紀の森と広場」の行事、「坂川河津桜まつり」などとの関連を探り、運営する側の人とのつながりを通して合わせて実施することなどによって観光客の広がりを期待できると思うがどうだろうか。